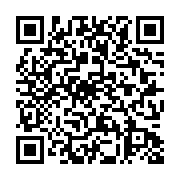腹式呼吸の3つのメリットのうちの一つ、「響き」についてです。
(他の2つは、「コントロール」「リラックス」の記事をご参照ください。)
声と言うのは、声帯で作った振動を色々なところに伝えて、そこを同時に振るわせることで増幅されて大きくなっています。
それを「共鳴」と言います。
体自体の振動はもちろんですが、一番大きいのは実は「空間」なんです。
空間として響く場所は、
・鼻(鼻腔)
・口(咽頭)
・ノド(喉頭)
・胸(胸郭)
などです。
そこの空間を響かせることによって、色々な声の響きの質感が作られます。
一般的に、口やノドを大きく開けましょうと言われるのはそのためです。
(※ただひたすら大きく開けるのが必ずしも「良い」わけではありません。単純に、響かせた声を作るという意味では空間を開けると響きやすくなるということです。)
アコースティックギターやバイオリンをイメージしていただけると分かりやすいかと思いますが、弦を鳴らした時に、弦が張られているボディ(木)の部分が振動し、同時にその中の空間で空気振動が起こります。
これによって大きな音になっているわけです。
このボディの部分がもし、中に空間が一切ない鉄のかたまりだったとしたら、ほとんど大きな音にはならないでしょう。
極端に言うと、胸式呼吸をした場合は、その鉄のかたまりに近いような状況になってしまうわけです。
そもそも体が硬くなって振動を殺してしまいますよね。
また、胸や肩が上がるので、ノドや口を開ける動きを妨げてしまいます。
要は、空間が狭くなって空気振動を減らしてしまうんですね。
腹式呼吸にすると上半身はリラックス出来ますし、空間を作りやすくなります。
なので、声の響きが作りやすくなる(響きの妨げになりにくい)わけです。
せっかく腹式呼吸をしていても、例えば口やノドが狭いなどのように、空間の作り方や響かせ方が出来ていなければ意味がありません。
腹式呼吸というのは、そういった諸々のコントロールをするために必要な、あくまでも最低限の『下地』なんですね。
だから、歌を始める時に必ず先に呼吸法をやるわけです。
腹式呼吸を学んだら、それがなぜ必要で、何に役立つのか、どう使うのか、これをしっかり理解して活用してくださいね!